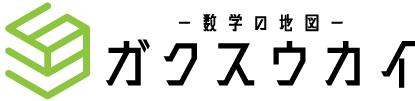[1] 12月のテーマ
テーマ:n進法という概念(part2)~計算方法から考える九九という発明~
今回は先月のn進法の第二弾になります。前回は「数の表現方法」というものの歴史をひもといて現代に至るまでの流れ等について扱いました。今回は具体的な計算を行うと同時に、我々が普段使っている10進法というものが特別にキリの良いものではないということについて考えてみました。キリが良いと感じる理由についても説明をしました。
[2] より深い理解のために
正方形の中に綺麗におさまるように各個人でボールを敷き詰めてみます。そうすると一辺にボールは何個入ったでしょうか。これが10個なら10進法ということです。この例でわかるように、ボールが9個でも4個でもどのような数でもきれいにおさまることがわかると思います。つまり10で桁の位が上がるということは、ただ慣れているだけであって特別に分かりやすいものではないのです。ただ掛け算などは明らかに10進法がやりやすいですが、これの理由が九九になります。
[3] 日常に仕掛けられたトリック
九九を習ったときは小学生なので、特別その意味であったり深いことを考察するようなことはあまりないかもしれません。九九というのはどの小学校もかなりはやい段階で習いますが、これをすることによって、その後の筆算が格段にやりやすくなります。そしてなぜ我々が「九九」を学んだかというと、日常が10進法であるからです。もし日常が7進法の世界であったら、我々が学ぶものは「六六」というものになっていたでしょう。その世界では10が特別にキリの良い世界ではありません。