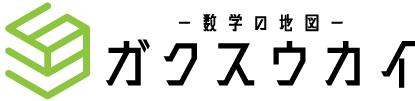[1] 10月のテーマ
テーマ:数学の出発点の定義と公理(part1)〜1+1=2は証明できるのか〜
今回は普段学校の授業ではあまり気にすることのない公理という内容に関する話を扱いました。公理と混ざりやすいこととして定義というものがあります、そして公理と定義から導かれる定理といったものがどのようなものなのかなどについても具体的な例を挙げて理解を深めました。これらの議論は非常に論理的なので、数学における論理的思考力を身に付けるためには意味がある内容となっています。
[2] より深い理解のために
物理学や化学や生物学と違い、数学というものは何か実際にある現象を考えるものではありません。あくまで人間が作り出した概念になっています。そのため、他の理学における基本法則はなく、人間が何かしらの取り決めをして議論を進めていく必要があります。それらのスタート地点をはっきりさせることで、その後は学校の授業で扱う論理と命題の内容に従って、論理展開をしていくことができます。今日の内容踏まえると、数学が哲学などに近いということもなんとなく理解ができるかもしれません。
[3]数学科と応用数学科
講座で取り上げた内容の数学そのものの厳密性やルール作りといった内容は、大学では数学科で学ぶものとなっています。大学で学ぶ数学は大きく分ければ二通りあり、純粋数学と応用数学があります。今回の内容は純粋数学ですが、応用数学は今日の話とは違い、数学を用いて何ができるかであったり数学を現実の世界に応用していく話などを扱います。ちなみにプログラミング等の内容は応用数学の学科で学ぶこともできます。