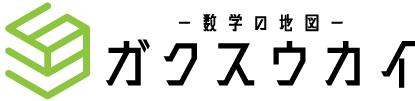[1] 9月のテーマ
テーマ:くじ引きの公平性〜確率によって検証する日常的問題〜
前回は場合の数と確率では根本的に数え方が違うという話を、確率論の歴史から紐解く形でおさえました。今回は確率同士が関係してくる話をはじめに行い、その後でくじ引きの確率を考えました。最後に日常に存在する宝くじなどを例として挙げました。
[2]より深い理解のために
確率を考えることで、いろいろな仕組みを理解することができます。例えば、くじ引きなどは日常でもよくありますが(席替えなどでも使用されますね)、これらの公平性についてしっかり考えた事はあまりないのではないでしょうか。講座でも意見があったように、感覚的には真ん中あたりで引く方が当たる確率は1番高そうですが、実際に計算してみるとどこで引いても同じことがわかると思います(3人めに当たる場合などは計算は大変でしたが結果が同じになるのは面白いですよね)。くじ引きという何気ないことも、確率によって公平性が保たれているからこそ成立するとわかります。
[3]感覚に惑わされないことの重要性
最後に講座では間違いやすい話の例として、コインで連続9回表が出ているときに次に表が出る確率が低いのかどうかなどを挙げました。これはくじ引きで真ん中が当たりやすそうに感じる心理と似ています。ただこちらはすでに連続で9回表が出てしまっているので、その確率は通常で表が出る確率と変わりません。このようにして条件が少し違うだけでも、問題の構造が大きく変わることがあることに注意が必要です。